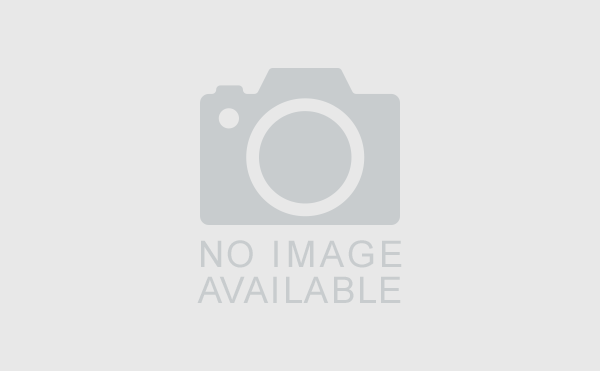過活動膀胱の鍼・整体治療
過活動膀胱とは
過活動膀胱とは、尿意切迫感(急に尿がしたくなり、我慢できない状態)を必須症状とし、通常は夜間頻尿や頻尿を伴う疾患です。
日本排尿機能学会が2002年に実施した排尿に関する疫学調査によると、40歳以上の12.4%(約810万人)が罹患しているとされ、加齢とともに増加します。
この結果を現在の人口構成で再計算すると、約1000万人以上となります。
さらに、810万人のうち約420万人は尿失禁を伴っており、特に外で働く方にとっては大きな負担となっています。
過活動膀胱の症状は
- 尿意切迫感(急に起こる、我慢できないような強い尿意)
- 頻尿(昼間頻尿・夜間頻尿)
- 尿失禁症状
過活動膀胱診療ガイドライン
病気の治療や検査に関するエビデンスに基づいた推奨事項をまとめた診療ガイドライという本があり、過活動膀胱診療ガイドラインの最新版は2022年版となります。
このガイドラインには推奨グレードというものがあります。

このガイドラインでは、鍼治療の推奨グレードはC1(行ってもよい)とされています。C1の表現は資料によって多少異なり、「科学的根拠はないが、行うよう勧められる(質の劣る論文あり)」「行うことを考慮してもよいが、十分な科学的根拠がない」などの記載があります。
また、このガイドラインには「仙骨神経刺激療法」という治療法が記載されています。これは、仙骨孔(第三仙骨孔)に挿入した刺激電極を用いて仙髄神経を継続的に電気刺激し、下部尿路機能障害や排便機能障害の症状を改善する治療法です。推奨グレードはAとされています。仙骨神経刺激装置を埋め込む手術となり、2017年に難治性過活動膀胱に対し保険適用となっております。
これとは別に後脛骨神経刺激療法の記載もあります。後脛骨神経は先程の第三仙骨孔から出る神経にあたり、その支配領域の末端部分に電気刺激をかけるというものですが、これには足にある三陰交というツボを使っています。こちらの推奨グレードは保留となります。保留とはなっておりますが、有効であったという論文があります。
過活動膀胱の鍼灸・整体治療
鍼治療では、上記の仙骨神経刺激療法で用いられる仙骨孔(主に第三仙骨孔)に、「中髎穴(ちゅうりょうけつ)」が存在します。この部位に鍼を刺入し、電気刺激を加えることで治療を行います。さらに、東洋医学的な治療を組み合わせることで、概ね数回の施術で効果を感じられることが多いです。
整体治療は腰椎・仙腸関節の調節をしていきます。
来院時に過活動膀胱のチェックシート、排尿シートをご記入のうえ、ご持参いただけると、より正確に状態を把握することができます。
参考資料