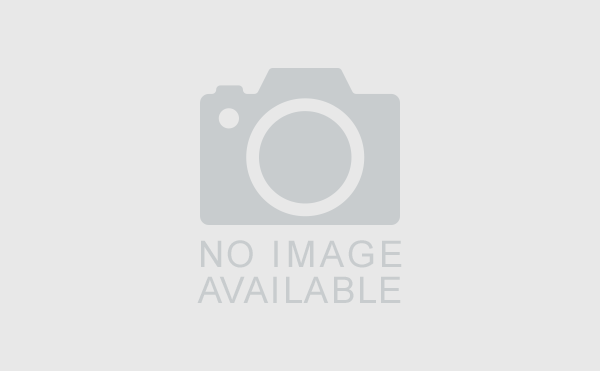慢性疼痛
慢性疼痛とは
治療に要すると期待される時間の枠を超えて持続する痛みとされ、概ね3ヶ月以上続く痛みとなります。
侵害受容器性疼痛、神経障害性疼痛。心理社会的疼痛などに分類されますが、慢性化すると痛みの要因はどれか1つに起因することは少なく、色々な要因が複雑に絡んだ混合性疼痛になります。
また、睡眠障害、食欲不振、便秘、抑うつ、不安、破局的思考などの症状を伴うことがあります。
慢性疼痛に対する鍼治療の効果
慢性疼痛に対する鍼治療のキーは「脳」です。
慢性疼痛を患っていらっしゃる方の脳をFDG-PETで検査すると
- 前頭前野の代謝低下
- 扁桃体の代謝亢進
- 海馬・海馬傍回の代謝亢進
また、否定的情動(恐怖、苦悩、不安など)は、扁桃体、海馬、海馬傍回の過活動をもたらし、中脳の腹側被蓋野から大脳基底核の線条体(側坐核など)への快楽に関与するドーパミンおよびオピオイドの分泌が低下します。さらに、痛みをコントロールする機能が破綻し、前頭前皮質の機能が低下すると、目標指向行動がとれなくなるとの報告もあります。
本来、人間には痛みを緩和させる生体防御機能が備わっているのですが、 痛みが持続したり、ストレスが強い場合は、脳に可塑性変化を起こし、その機能が低下します。
画像は耳介(三叉神経第1枝)に鍼刺激をした時に大脳皮質実質内の血流が増加している様子です。

こちらの画像は鍼に通電し電気刺激を与える時の周波数によって分泌される脳内オピオイドの種類が違うというものです。

Enk(エンケファリン)の作用
- 痛みの緩和(痛みの感受性を低下させ、筋肉の緊張を和らげます。これにより、身体のリラックス状態を促進し、痛みを軽減します。)
- ストレスの軽減(気分を安定させ、ストレスを軽減する作用があります。これにより不安や緊張が和らぎます。)
- 気分の調整
- 免疫機能の調整
Dyn(ダイノルフィン)の作用
- 痛みの制御
- ストレス応答の調整
- 情動と気分の調整
- 快楽の抑制
当院ではこれらの論文を参考にし、三叉神経第1枝への通電治療(周波数に変化を与えながら)、線維筋痛症への鍼治療の論文から四肢末端穴を使った治療を主におこなっております。
参考資料